なぜ今、論理的で正確な文章が必要なのか?
技術文書、ビジネス報告、部下への指示、社内外のメールに至るまで、私たちは日々 正確に意図を伝え、相手を動かす文章 の重要性を痛感しています。
曖昧な表現や主旨がブレた文章は、誤解を生み、仕事の効率と対外的な信頼を著しく低下させてしまいます。
私自身、管理的な立場に就いたこともあり、正しい日本語や文章を使える能力を自己の最重要課題と捉え、日々精進しています。
このブログも私がその探求を通じて得た、実践的かつ論理的な文章作成のステップを共有し、皆様の仕事の質が高まる一助となればという目的と自己成長も兼ねて執筆しています。
この探求を通じて得た実践的かつ論理的な文章作成の「骨子」を解説することで、皆様の文章作成のプロセスが改善され、仕事の質が高まれば幸いです。
ステップ1:いきなり書き出さない!「構成要素」を整理する
論理的かつ伝わる文章は設計図なしに生まれることはありません。
プログラミングにおけるモジュール設計のように、まずは頭の中にある情報を「構成要素(パーツ)」としてすべて整理し、可視化することから始めます。
書きたいことを箇条書きでアウトプット
思考の全量をマインドマップや箇条書きで漏れなく展開します。
これが、文章の素材集めです。
5W1Hで要素をトピック化する
「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰に(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」といった視点から要素を構造化します。
この準備が文章の核となる情報をブレさせないための土台作りになります。
ステップ2:要素・順序・軽重—伝わる文章の「骨子」を設計する
集めた要素を読者の理解を促すよう論理的に組み立てる、文章の「骨子」を設計します。
重要なのは 要素、順番、軽重 の順で決めていくプロセスです。
要素の選定:話のポイントと論点を明確にする
主張、根拠、事例など、各トピックで最も伝えたい核心部分を選定します。
順序の決定:話の段取り(流れ)を考える
話の導入→本論→結論といった流れや、重要な情報から伝える構成を意識し、読者が無理なく論理を追える順番を決定します。
軽重の調整:主題への注力度合いを決める
情報の重要度に基づき、最も伝えたい主題には深く掘り下げるウェイトを置き、補足的な情報には簡潔に留めるなど、話の分量と熱量のバランスを調整します。
ステップ3:推敲で曖昧さを排除し正確性を高める
骨子に基づいた文章が完成した後、最も重要なのは推敲(文章をよくするために読み返して修正すること)です。
読者は途中から読むことはありません。
面倒でも必ず段落や章の頭から読み直すことで、修正による前後の流れの悪化や、言葉のねじれがないかを確認します。
特に曖昧さを排除し、正確性を高めるために注意したい日本語の運用ルールを以下で解説します。
主語の「は」と「が」の厳密な使い分けをする
この助詞の使い分けは文章のニュアンスを大きく変えます。
「は」は他との比較や対比を暗に含みます。
例:空は青い(”しかし海はもっと濃く青い”などの比較を含む)
一方「が」は範囲を特定し、その事象をそのまま述べる場合に使われます。
例:空が青い(断定的であとに比較や対比を含まない)
意図しない対比や限定を防ぐため、常にどちらが適切か判断することが大切です。
体言止め(名詞止め)の潜むリスクを理解する
体言止めは文章を簡潔にしますが、読者の頭の中で動詞を補完させるため、誤解の可能性を秘めています。
例えば、「XXXが新しい企画を発表」と書かれた場合、読者が
「発表(する)」、「発表(した)」、「(発表された)」のいずれかを補完しなければならず、ニュアンスが誤って伝わるリスクがあります。
明確さが求められるビジネス文書では、動詞を省略しない方が賢明です。
不必要な読点と丸カッコの排除
文頭の一語目に続く読点を控える
「また、〇〇では、」といった一語目に続く読点は、極力控えた方がスマートに見えます。
「また」の後に読点を打つことは、小学校でも教えられたと思いますが、内容を考えながら話す人の話言葉に似ていることから、文章を幼く見せる可能性があるそうです。
ここについては少々好みもあると思います。
丸カッコ()による説明の多用を避ける
本筋から逸れた補足説明を丸カッコなどを用いると、読者にメタ言及的な印象を与え、本論への集中を妨げます。
必要な情報は極力、本文に組み込みましょう。
まとめ:魅力的な文章の秘訣とは?
最終的に読者を惹きつけ、完読させるための魅力的な文章の鍵は、読み手の想像力を刺激することにあります。
単なる筆者の「感想」や「主観的な思い」の表明に留まるのではなく、情景や事実を客観的に描写することも意識して作ることが大切です。
それにより読者はそこに潜む論理や背景を自ら推測し、「なるほど」と納得感を深めやすくなります。
基本ルールを徹底しながらも、日々の読書を通じて表現力を磨き、読者の目線に立った文章の探求を続けることこそが、仕事の質を高め、信頼を築く文章力向上の道であると信じています。
参考になった書籍
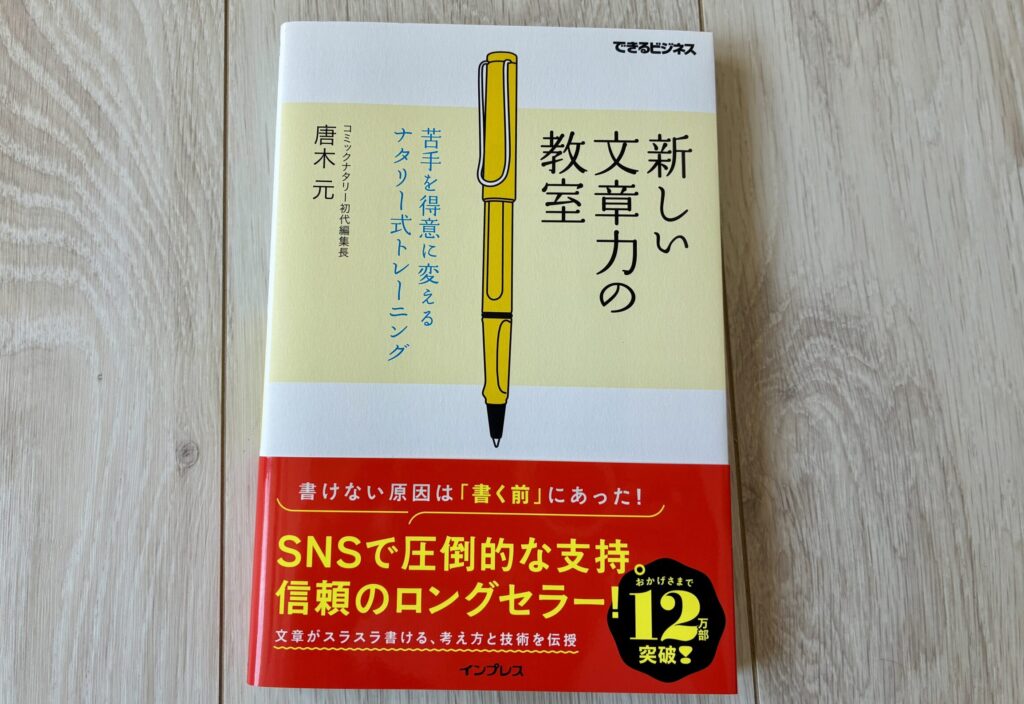
新しい文章力の教室 著者:唐木 元 ⇒ Amazonリンク

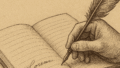

コメント